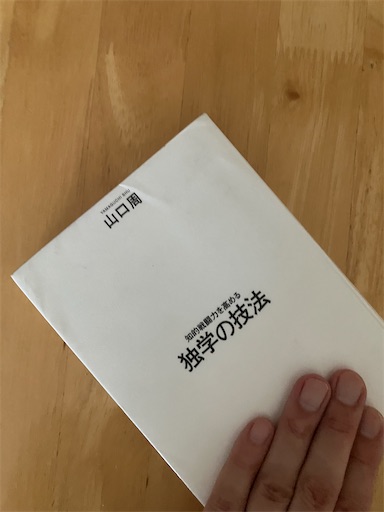
思うに私は、価値のあるものは
すべて独学で学んだ。
独学で重要なことは「覚えること」を目指さないこと。「知る」ことは時代遅れになりつつある。覚えたことを実践で使えるようになることの方がよっぽど大切。
①知識の不良債権化
学校で学んだ知識は急速に時代遅れになる
②産業蒸発の時代
イノベーションはいまの仕組みを根底から覆す。iPhoneというイノベーションにより、ガラケーメーカーがビジネスを失う。市場からいなくなった蒸発した状態。
③人生三毛作
労働時間は長くなるのに企業の「旬の寿命」は短くなる。人生100年時代なのに、次々と新しい技術が出る。仕事のやりがいや経済的報酬、精神的な安定、人生の豊かさなど、波に飲まれるかどうか、独学の重要性がある。
④クロスオーバー人材
二つの領域を横断・結合できる知識が必要となる。スペシャリストもゼネラリストも、異質と思われた二つ以上の領域を対応できる人材が必要となる。
独学のメカニズムは
①戦略
どのようなテーマについて知的戦闘力を高めようとしているのか、その方向性を考えること
↓
②インプット
戦略の方向性について、本やその他の情報ソースから情報をインプットすること
↓
③抽象化・構造化
インプットした知識を抽象化したり、他のものと結びつけたりすることで、自分なりのユニークな示唆・洞察・気づきを生み出すこと
↓
④ストック
獲得した知識と、抽象化・構造化によって得られた示唆や洞察をセットとして保存し、必要に応じて引き出せるように整理しておくこと
「愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ」
ドイツの鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルク
人の振る舞いを研究するのは、一般にコレを行動心理学と言い、組織の振る舞いを研究するのは、一般にコレを社会心理学というが、歴史を学ぶ意味は「人や組織の振る舞い」について、過去の事例をもとにして考察する学問。
「考察」抜きに雑学的に知識を仕入れても人は組織の振る舞いにおける洞察は得られない。
悪い中間管理職は数少ない知識と狭い範囲の自分の経験だけに基づいた自己流の考えに凝り固まってしまっている。
インプットは学び
抽象化・構造化は思う
この学ぶと思うのバランスにより独学のシステムが完成する
①戦略
・武器を得るにはどうするか?
戦略を立てて武器を見つける。作者山口周は「人文科学と経営科学の交差点で仕事をする」と決めて、その二つの知見を組み合わせて、他の人と異なる示唆やどうさつをだし、それをコンサルティングやワークショップに使う。
・独学をするには余計な知識はいれない。政治的ゴシップなど。知らないと恥をかくなど無視をすれば良い。時間には限りがあるから
・知的戦闘力の向上は独学の戦略を決めること。インプットの有無を明確にすること。
②インプット
テーマが「主」ジャンルが「従」
ジャンルとは心理学とか経済学とか、テーマとは自分が学びたい論点
例えば山口周のテーマは「イノベーションが起こる組織とはどのようなものか」など。
テーマとジャンルはクロスオーバーすると、元のジャンルと得られる学びのジャンルをジャンプさせる。つまり、さまざまなジャンルの知識が組み合わさり、独自の示唆や洞察が生まれる。
・老害とは知識のアップデートに失敗した人
・ビジネス書は狭く浅く読む
自分が決めた本や著者を反芻することでそれが身につくのでノートはいらない
・教養書は雑多に読みしっかりノートにとる雑多に読むので忘れやすいのでしっかりメモしておく
・よくわからない知識も入れておくことで、後で繋がることがよくある。イノベーションも結果として起きたことばかり、ライト兄弟の飛行機とかエジソンの蓄音機(速記や遺言が元々の目的)とか。無意味な勉強も後で生きることがある。
・インプットされた内容は、基本的に全て忘れる
効率の良い読み方は、関連分野を固めてよむこと。
・情報は量より密度、余計な情報は入れない。実は人と話すことが最も良いインプット
・問いのないところに学びはない。自分らしい問いを持つこと。
・なぜメモが大事かというと、メモが癖になると、感じることも癖になるからだ。人より秀でた存在になる不可欠な条件は、人より余計に感じることである。 野村克也
③抽象化・構造化
・抽象化とは、細かい要素を捨ててしまってミソを抜き出すこと。「要するに◯◯だ」とまとめてしまうこと。モノゴトがどのように動いているか、その仕組み=基本的なメカニズムを抜き出すことです。経済学ではこれを「モデル化する」という。
・モデルとは本質的なものだけを強調して抜き出し、あとは捨て去る作業。
・抽象化は個別性が低下した状態。色々な状況に適応して考えることができる。
・知的戦闘力が上がるとは、ある局面において同じ量の情報を与えられた他者と比較して、より良い意思決定ができることに他ならない。
・得られた知識は何か、その知識の何が面白いか、その知識を他の分野に当てはめるとしたら、どのような示唆や洞察があるかを考える
④ストック
インプットした情報は記憶しようとせず、デジタルデータにストックしていつでも出せるような状態にすること。タグ付けしていつでも出せるように目印をつけること。
・イノベーションを駆動するには「常識への疑問(常識を疑う、why?と思う)」がどうしても必要になり、「見送って良い常識」と「疑うべき常識」を見極めることが「厚いストック」である。
・「厚いストック」は昔の人は官僚や宦官などに知識をもたせるようにしていた
・アナロジーという異なる分野からアイデアを借用する、いわゆる「パクリ」を行うこと。ストック次第でアナロジーは無限大に広がる。クリエイティブな人というのは、実はアイデアをつなぎ合わせているだけ、という可能性がある
・コレは!?と思う情報をストックする。重要なのは、興味深い事実や、それらの深い示唆や洞察、それらから得られる行動。
・イノベーションにより古い知識となったものは捨てることも大切
リベラルアーツとは自由の技術である。その時その場所での支配的な物事を見る枠組みなど、目の前の世界において常識として通用して誰もが疑問を感じることなく信じきっている前提や枠組みを、一度引いた立場である相対化してみる。つまり「問う」「疑う」ための技術がリベラルアーツの真髄。
今まで正しいと思っていた前提を壊し、新たな価値を考えるイノベーションを発揮するためには、このリベラルアーツの発想が重要になる。
パソコンは量販店で売る常識を、コンパックやデルはダイレクト販売で崩した。
PCは入力機能と記憶媒体が必要と価格競争の泥沼にハマる電機メーカーと、その前提から離れたiPad。
①から⑤を実現することが知的戦闘力を高めることになる。
・知的戦闘力を高める学問
①歴史
原点回帰に必要な学問。歴史を知っていることが、取り組みを整理する上での原点回帰につながる。
・歴史家の自画像
・図説 世界の歴史
・歴史とは何か
・新装版 大英帝国衰亡史
・普及版 地中海
・銃 病原菌 鉄
・サピエンス全史
・中世の秋
・エーゲ 永遠回帰の海
②経済学
マイケルポーターの競争の戦略でも語られているように、価値という概念についての洞察を得られること。基本だが価値は需給バランスで決まることを抑えておく学問。
・日本人のための経済原論
・マンキュー経済学Ⅰ Ⅱ マクロ論(2冊)
・経済学の考え方
・エンデの遺言 根源からお金を問うこと
・貧困と飢餓
・経済学大図鑑
③哲学
哲学には必ず大きな否定が含まれている。哲学は世界のエリートのスタンダードで、全てに問いを持つことで、世の中で主流となっているものの考え方や価値観について「本当にそうだろうか?」「違う考え方があるのではないか?」と考えることが求められる学問。マインドフルネスも同じで「自分の中に湧き上がる、微妙な違和感に気づくのか大事」という考え方。
・哲学大図鑑
・寝ながら学べる構造主義
・世界十五大哲学
・バカの壁
・新訳 弓と禅
・竹田教授の哲学論 講義21講 21世紀を読み解く
・自由からの疾走
・理性の限界 不可能性・不確実性・不完全性
・史上最強の哲学入門
④経営学
思考プロセスを追体験しながらビジネスの共通言語を学ぶ。経営学は古い本で昔から原理は変わらない。それを抑えること。
・企業戦略論
・競争優位の戦略
・イノベーションの普及
・キャズム
・【新版】組織行動のマネジメント
・戦略の経済学
⑤心理学
人間がどう感じ、考え、行動するかという「不合理性」を知る。人間は合理的に振る舞わない。
・ファスト&スロー
・現代心理学Ⅰ
・心理学大図鑑
・社会心理学講義
・フロー体験 喜びの現象学
・影響力の武器「第三版」
・ポジティブ心理学の挑戦
・昔話の深層
・セラピスト
⑥音楽
全体構想の良し悪しを直感的に判断できる力を高める。良い戦略は、全体として美しい音楽のような調和を持っている。
・東京大学のアルバート・アイラー東大ジャズ講義録・歴史編
・小澤征爾さんと、音楽について話をする
・音楽の基礎
・西洋音楽史「クラシック」の黄昏
・音楽機械論
⑦脳科学
人間がしばしば起こすエラーを正確に予測する
・脳科学の教科書
・最新脳科学で読み解く 脳の仕組み
・進化しすぎた脳 中高生と語る「大脳生理学」の最前線
⑧文学
「実のある嘘」から人間性を深く理解する
・罪と罰
・嵐が丘
⑨詩
レトリックの引き出しを増やして「言葉の力」を身につける
・詩ってなんだろう
・詩のこころを読む
・地獄の季節
・みだれ髪
・中原中也詩集
・繰り返して読みたい日本の名詩
⑩宗教
特定の組織や個人の思考・行動パターンを理解する
・キリスト教神学入門
・日本人のための宗教原論
・新約聖書 新共同訳
11自然科学
新たな発見やビジネスの問題解決の糸口になる
・利己的な遺伝子(増補新装版)
・働かないアリに意義がある
・新版 動的平衡
・部分と全体
・生命とは何か
#メーカー営業目線
#NIer目線
#テレビ番組制作目線
#広告代理店営業目線
#広告代理店プランナー目線
#マーケッター目線
#元YKK
#元ネットマークス
#元テレビ番組制作
#元三井物産のスタートアップ
#元ADK